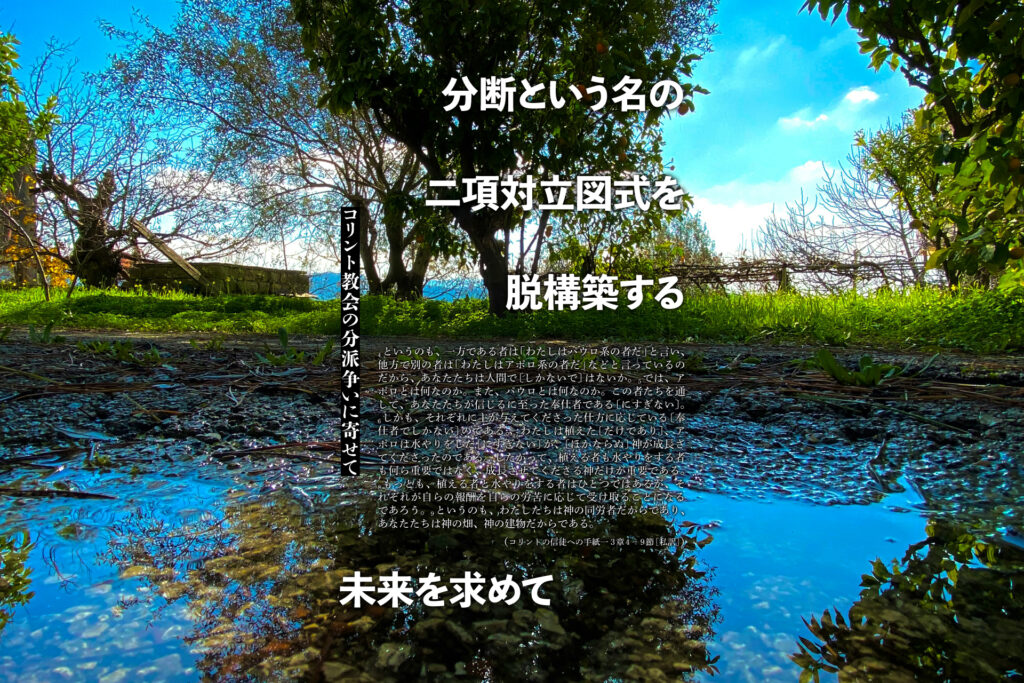分断という名の二項対立図式を脱構築する未来を求めて
――コリント教会の分派争いに寄せて――
4というのも、一方である者は「わたしはパウロ系の者だ」と言い、他方で別の者は「わたしはアポロ系の者だ」などと言っているのだから、あなたたちは人間で〔しかないで〕はないか。5では、アポロとは何なのか。また、パウロとは何なのか。この者たちを通して、あなたたちが信じるに至った奉仕者である〔にすぎない〕。6しかも、それぞれに主が与えてくださった仕方に応じている〔奉仕者でしかない〕のである。7わたしは植えた〔だけであり〕、アポロは水やりをした〔にすぎない〕が、〔ほかならぬ〕神が成長さてくださったのである。したがって、植える者も水やりをする者も何ら重要ではなく、成長させてくださる神だけが重要である。8もっとも、植える者と水やりをする者はひとつではあるが、それぞれが自らの報酬を自らの労苦に応じて受け取ることになるであろう。9というのも、わたしたちは神の同労者だからであり、あなたたちは神の畑、神の建物だからである。
(コリントの信徒への手紙一 3章4−9節[私訳])
Ⅰコリント書は教会内の格差や意見の違いなどを解決するためにパウロが書いた手紙です。引用したⅠコリント書3章4−9節からもコリント教会内部に分派争いがあったことが分かります。この部分のギリシャ語は言葉足らずであり、翻訳するうえでは少々厄介ですが、パウロが言わんとする意味は明瞭です。自分たちは神の同労者であり、その働きには神によって与えられた違いもありはするが、神のもとでひとつの目標に向かっているのだから、アポロ派やパウロ派などの取るに足りないことに拘ることを止めて、神に属する者として、目標に向かって歩もうとの呼びかけです。
キリスト教の小部屋でこのような建徳的な聖書テクストが取り上げられるのは稀ですが、この背後には分断され続けている世界に対する担当者の逼迫した危機感があり、それは取りも直さず、分断によって命が奪われ続けている世界の惨状に対する深い悲しみと怒りに溢れた思いでもあります。このような分断の潮流は、世界の各地で続く戦争の現実によって最も鮮明に映し出されていますが、日本やアメリカの選挙結果からもひしひしと伝わってきます。そして、時代を先取りするかのように、分断の潮流は日本基督教団の歴史に絶え間なく押し寄せてきました。
2024年10月29〜31日に第43回日本基督教団総会が開催されました。総会は二年に一度開催される教団の最高の意思決定機関ですが、近しい人から聞いたところでは、スタンスの違いを超えることのできない平行線を辿る議論が続き、何の前進もない徒労感の漂う日々であったとのことです。もちろん、これはその人の個人的な感想であり、むろんその場にいた人たちは真剣に議論をし、自らの思いの丈を表白したのだとは思います。しかし、その人が言うには、このような教団内部のスタンスの違いは、端から眺めると、同じにしか見えないのではないかというのです。それをわたしなりに理解すれば、現在の日本の政党政治において、大局的には保守とリベラルの二項対立図式などはもはやなく、同工異曲を奏でているようにしか感じられないのと同じように、教団内部の議論も異曲同工にしか聴こえなくなってしまっているということです。
おそらく、このような教団の状況は、日本の政党間の議論がそうであるように、同一の目的や目標が存在せず、それゆえに共通言語を持つことが叶わず、意を尽くして話し合うという厄介なことを避け、異なる意見を封殺するという安易な方法を取ってしまっていることに起因し、その弊害が狭い組織内部のヘゲモニー争いとして立ち現れているのです。しかし、教団内部での立場の違いなど、端から眺めると、存在しないに等しいものでしかないのです。それはパウロがアポロ派もパウロ派もなく、全て神に属していると宣言する内容に通じるものでもあります。そして、このような見立ては、キリスト教主義大学に奉職する教団の教務教師でもあるわたしにとっても、学内の大部分を占める非キリスト教徒の教職員からすれば、学内のキリスト教徒がいずれも同じに見えているであろうことを実感していることからしても、頷かざるを得ない現実でもあります。
Iコリント書を著したときのパウロは、世の終わりが近いという終末思想に取り憑かれていたということもあり、内部で争っている場合ではないと怒り心頭になり、却って教会内部の争いに火に油を注いでいるようにも見えなくもありませんが、大切なのはアポロでもパウロでもなく、神なのだというパウロの言葉は、人間を絶対視しない――ある種イエスとも通底する――重要な視点を提供してくれます。この時点のコリント教会は発足して間もない小さな集まりに過ぎませんでしたが、その小さな集団でさえも、分派争いが絶えることがなかったことが分かります。発足から80有余年の日本基督教団は吹けば飛ぶような小さな組織かもしれませんが、コリント教会に比すれば遥かに大きな組織だと言えます。その教団に分派争いやヘゲモニー争いがあっても別に不思議なことではありません。しかし、このような現実を直視するとき、怒ったり泣いたりしながら、コリント教会の分派争いに倦むことなく関わり続けたパウロの姿は、今の教団が真剣に向き合うに値する生き方を示していると言えます。
戦争に満ちた現代世界において、第三次世界大戦の危機さえも叫ばれる状況はまさに終末の様相を呈しているかのようです。このような時代状況において、教団はパウロからアポロ派もパウロ派もないと怒り心頭に説教されているようにさえ思えるのです。端から眺めたら同じにしか見えないにもかかわらず、わたしたちはいったい何に拘り、何のために拘っているのでしょうか。戦争によって命を奪われている現実の直中において、キリスト教の求める「平和」は「社会の平和」か「キリストの平和」かという――端から眺めれば、同じにしか見えない――二項対立図式のアポリアから抜け出すためにも、現在の教団が実践する平和の活動に全力を注ぎつつ、そのうえで聖書主義に立つプロテスタント教会として、分派争いを戒めるパウロの言葉に傾聴し、その働きの違いを神から与えられた違いとしてパウロが是認しているように、わたしたちもまた立場や意見の違いを相互に受け入れ、意を尽くして聞き合い、意を尽くして話し合うことで、これまでの分断という名の二項対立図式を脱構築する新たな未来を求めていくことが必要ではないでしょうか。(小林昭博/酪農学園大学教授・宗教主任、デザイン宗利淳一)