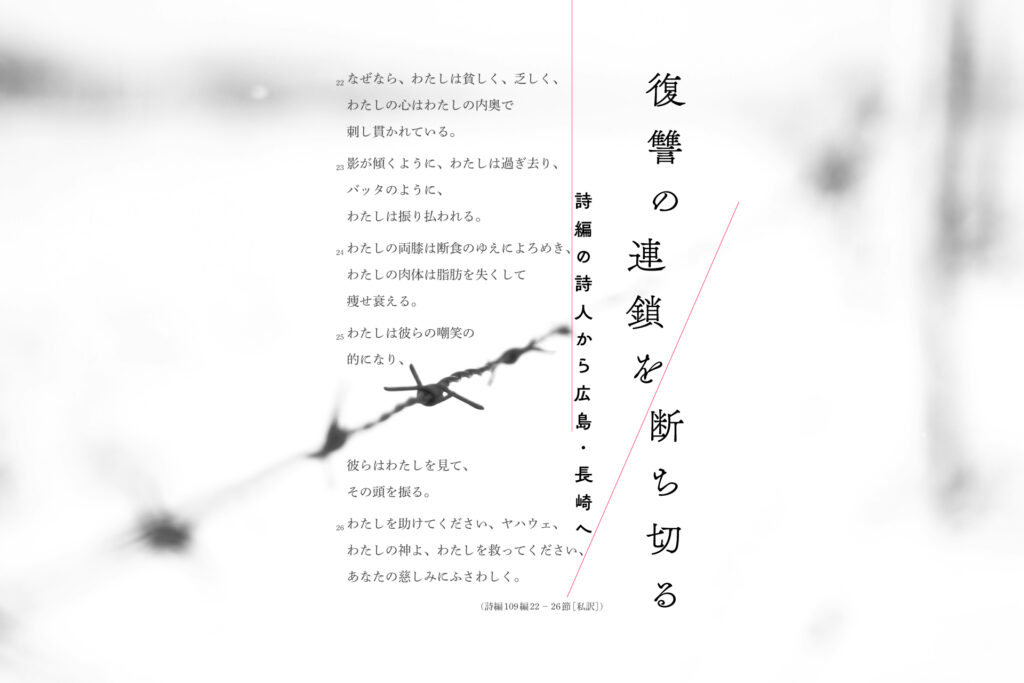
復讐の連鎖を断ち切る
――詩編の詩人から広島・長崎へ――
22なぜなら、わたしは貧しく、乏しく、
わたしの心はわたしの内奥で刺し貫かれている。
23影が傾くように、わたしは過ぎ去り、
バッタのように、わたしは振り払われる。
24わたしの両膝は断食のゆえによろめき、
わたしの肉体は脂肪を失くして痩せ衰える。
25わたしは彼らの嘲笑の的になり、
彼らはわたしを見て、その頭を振る。
26わたしを助けてください、ヤハウェ、わたしの神よ、
わたしを救ってください、あなたの慈しみにふさわしく。
(詩編109編22−26節[私訳])
詩編109編は6−19節に呪詛の言葉が連ねられていることから、長らく「呪いの詩編」と呼ばれてきました。そこでは腐敗した権力者たちによって法廷に引き摺り出された詩人が呪詛の咆哮を浴びせられています。
冒頭に引用した22−26節は呪詛の言葉の直後に置かれており、自分を陥れた権力者たちによって葬り去られようとしている詩人の祈りが綴られています。この詩人は社会的・経済的な立場を奪われただけではなく、精神的にも追い詰められ(22節)、影が夜の闇のなかに消え去るように、あるいは邪魔なバッタが振り払われるように、葬り去られる運命にあるというのです(23節)。詩人は不当な訴えに抗して食を断ち、立ち上がる力もないほどに衰弱し(24節)、嘲笑の標として敵対する者たちから頭を振られて愚弄されます(25節)。しかし、詩人は迫り来る死の影に飲み込まれそうになりながらも、神に救いを祈っています(26節)。
このように詩編109編において詩人は敵対者たちの呪詛に呪詛を返すことはせず、引用した22−26節のすぐ後では、敵対者たちが呪いを与えるのに対して、神は祝福を与えると述べることで(28節a)、復讐の連鎖を何とか断ち切ろうとしているのです。
しかしながら、キリスト教は詩編109編を自らに敵対する者たちに対する呪詛を正当化するために用いてきた歴史があります。その典型は使徒言行録1章20節に引用されている詩編109編8節に関する拡大解釈です。使徒言行録1章20節では、ペトロの口からイスカリオテのユダの死地が「アケルダマ」(血の土地)という呪われたものになったことが語られているのですが、ペトロの発言を拡大解釈して、古代の教父たちは詩編109編をイスカリオテのユダと関連づけて読むようになり、詩編109編は「イスカリオテの詩編」(Psalmus Ischarioticus)と名づけられるようになったのです。しかも、キリスト教は「イスカリオテのユダ」を「ユダヤ人」の原型と見なし、それがそのままキリスト教のユダヤ人に対する呪詛とユダヤ人迫害を正当化する聖書的根拠とされるようになったのです(エーリヒ・ツェンガー)。
この復讐の連鎖は今も続いています。キリスト教がユダヤ人を理不尽に迫害したように、キリスト教は「イスラム嫌悪」(Islamophobia)によってイスラム世界を呪ってきました。そして、その復讐の連鎖はさらに形を変え、イスラエルによるパレスティナ侵略として、1947−1948年から現在のガザ侵略に至るまで続いています。
このような歴史を振り返ると、呪いや復讐の連鎖を断ち切ることよりも、呪いや復讐に身を委ねることの方がたやすいだけではなく、それを正しいと感じてしまっているのが人間という存在だと言わざるを得ないのです。
終戦から79年目の8月を迎えます。侵略戦争の過ちを認めて反省することが自虐史観と言われることすらなくなるほどに、かの戦争が正当化され、アジア周辺諸国に対する呪いが復讐の連鎖のように日常に侵食しています。呪いと復讐の連鎖が観念ではなく、現実になるとき、それはガザやウクライナで起こっている現実のように、人の生命は血と肉塊になり、跡形もなく消し飛ぶ阿鼻叫喚が目の前に広がるのです。その最も非道な現実を経験した被爆地の広島と長崎が、呪いと復讐に身を委ね、死と戦争の影に飲み込まれてしまっていたとしても、おかしなことだったとは言えません。しかし、広島と長崎は二度と核兵器が使用されることのないように求め、二度とあの過ちを繰り返さないように願い続けています。その姿は復讐の連鎖を断ち切ろうとする詩編の詩人と重なり、死と戦争の影に飲み込まれてしまいそうな自分に呪いと復讐の連鎖を断ち切るよう迫っているように思えるのです。(小林昭博/酪農学園大学教授・宗教主任、デザイン宗利淳一)







