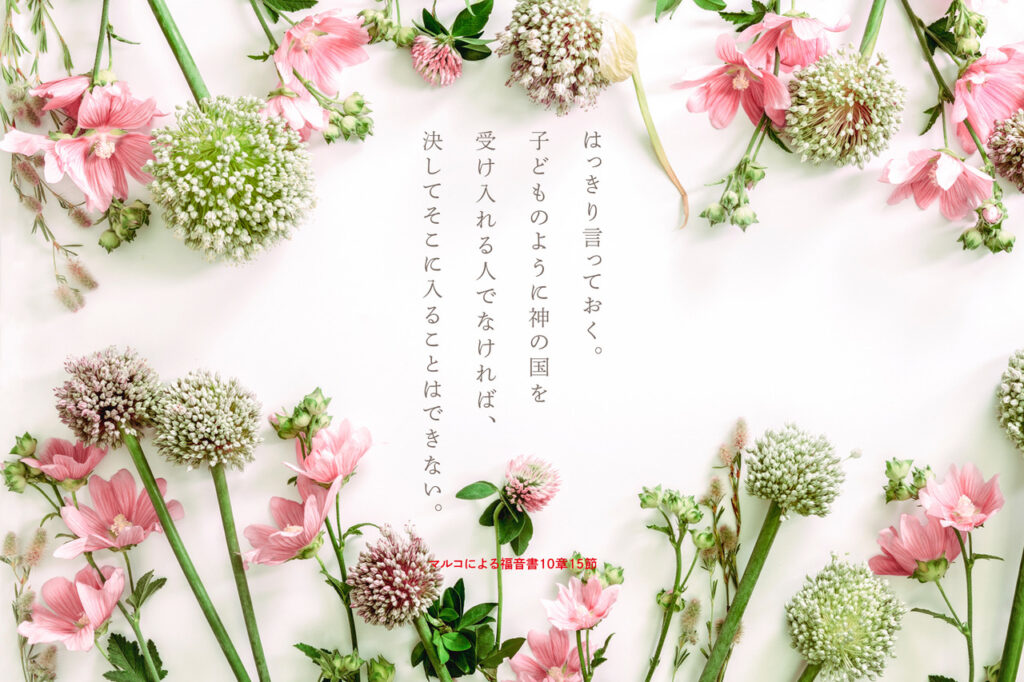
子どもが大切にされる今を
——子どもの日(花の日)に寄せて——
アーメン、わたしはあなたたちに言う、子どもを受け入れるように神の国を受け入れる者でないのならば、そこに入ることは断じてない。
(マルコ福音書10章15節[私訳])
「子どもを受け入れるように」と訳したテクストは、「子どもが〔神の国を〕受け入れるように」と翻訳することも可能であり、それが通常の理解とされています。つまり、子どもが無垢で無力なままで神の国を受け入れる姿が模範として示されているとの解釈です。しかし、この科白(ロギオン)はイエスに触れてもらおうと近づいてきた子どもたちを妨げた弟子たちに向かって、子どもを抱き上げながら発せられたものですので、私訳のように理解するのが至当です(マルコ福音書9章37節参照)。子どもを受け入れるという当たり前に思えることが、実は古代世界では当たり前ではなく、むしろ弟子たちの態度が普通だったのです。子どもが子どもとしてその存在が認知されるのは近代になってからであり、特にこのテクストで言及されているのが「幼な子」(パイディオン)を表すことを考えると、子どもを大切にするイエスの思いは、神の国の未来にではなく、その生命さえも軽んじられていた「幼な子」を大切にする現世の今に向けられていたのです。6月の第2日曜日の「子どもの日」(花の日)を迎えるに当たって、子どもたちが大切にされる今を願わずにはいられません。(小林昭博/酪農学園大学教授・宗教主任、デザイン宗利淳一)







