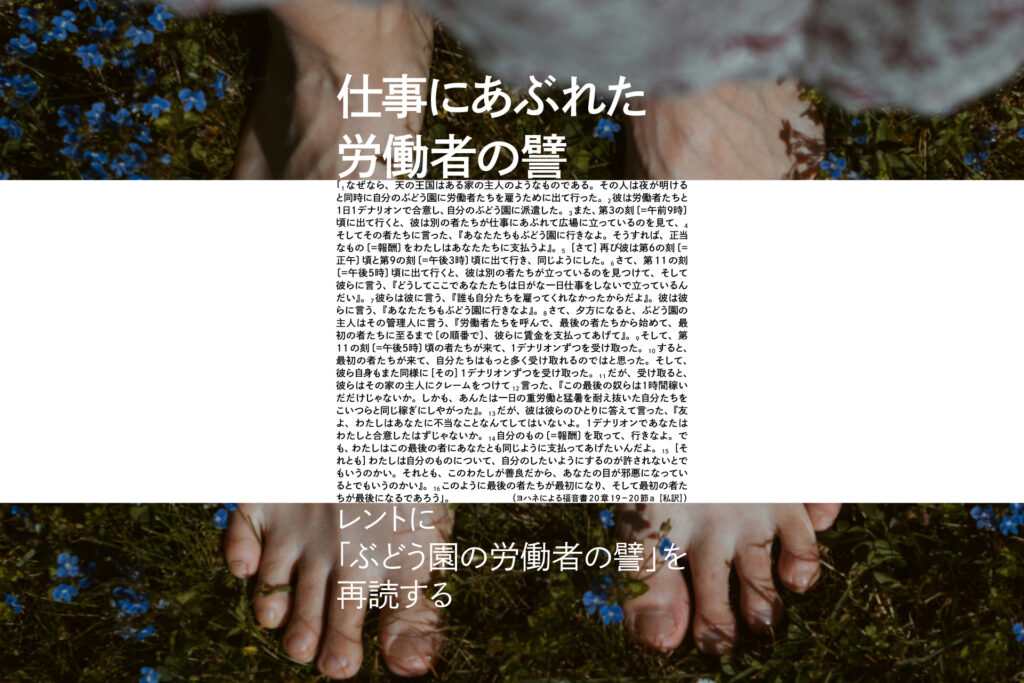仕事にあぶれた労働者の譬
――レントに「ぶどう園の労働者の譬」を再読する――
「1なぜなら、天の王国はある家の主人のようなものである。その人は夜が明けると同時に自分のぶどう園に労働者たちを雇うために出て行った。2彼は労働者たちと1日1デナリオンで合意し、自分のぶどう園に派遣した。3また、第3の刻〔=午前9時〕頃に出て行くと、彼は別の者たちが仕事にあぶれて広場に立っているのを見て、4そしてその者たちに言った、『あなたたちもぶどう園に行きなよ。そうすれば、正当なもの〔=報酬〕をわたしはあなたたちに支払うよ』。5[さて]再び彼は第6の刻〔=正午〕頃と第9の刻〔=午後3時〕頃に出て行き、同じようにした。6さて、第11の刻〔=午後5時〕頃に出て行くと、彼は別の者たちが立っているのを見つけて、そして彼らに言う、『どうしてここであなたたちは日がな一日仕事をしないで立っているんだい』。7彼らは彼に言う、『誰も自分たちを雇ってくれなかったからだよ』。彼は彼らに言う、『あなたたちもぶどう園に行きなよ』。8さて、夕方になると、ぶどう園の主人はその管理人に言う、『労働者たちを呼んで、最後の者たちから始めて、最初の者たちに至るまで〔の順番で〕、彼らに賃金を支払ってあげて』。9そして、第11の刻〔=午後5時〕頃の者たちが来て、1デナリオンずつを受け取った。10すると、最初の者たちが来て、自分たちはもっと多く受け取れるのではと思った。そして、彼ら自身もまた同様に[その]1デナリオンずつを受け取った。11だが、受け取ると、彼らはその家の主人にクレームをつけて12言った、『この最後の奴らは1時間稼いだだけじゃないか。しかも、あんたは一日の重労働と猛暑を耐え抜いた自分たちをこいつらと同じ稼ぎにしやがった』。13だが、彼は彼らのひとりに答えて言った、『友よ、わたしはあなたに不当なことなんてしてはいないよ。1デナリオンであなたはわたしと合意したはずじゃないか。14自分のもの〔=報酬〕を取って、行きなよ。でも、わたしはこの最後の者にあなたとも同じように支払ってあげたいんだよ。15、[それとも]わたしは自分のものについて、自分のしたいようにするのが許されないとでもいうのかい。それとも、このわたしが善良だから、あなたの目が邪悪になっているとでもいうのかい』。16このように最後の者たちが最初になり、そして最初の者たちが最後になるであろう」。
(マタイによる福音書20章1−16節[私訳])
この譬話はとにかく評判が悪い。その一因は朝から晩まで1日中働いた者と1時間しか働いていない者が同じ賃金を受け取っていることにあるようです。いくら合意(契約)のうえで働いているとはいっても、これではあまりに不公平だというのです。時給制にしたり、個々の働きに応じたりして、賃金の差を設けるのが正しい経済であり、賢い経営者ということでしょうか。
あるいは、このぶどう園の主人が自分のもの(財産)を自分の好きなように使うのは当然だという物言いに含まれる高飛車で尊大な態度を不当に感じてしまうことも不評の一因だと言えます。この観点から考えると、ここで結ばれている合意(契約)そのものに資本家――現代の富裕層や上級国民――の上から目線の傲慢さを直感して嫌悪してしまうということでしょうか。
また、別の見方をすると、一所懸命にたくさん働く者とサボって全然働かない者に同じ給料が支払われているのが我慢ならないとの思いから、この譬話に納得がいかないとも考えられます。これはどの職場からも聞こえてくる嘆きであり、「働き蟻の法則」が脳裡に浮かびます。働き蟻の法則とは、働き蟻の集団では常に働く蟻が2割、普通に働く蟻が6割、常にサボっている蟻が2割であり、そしてこの割合はそれぞれの集団の蟻だけを集めて新たな集団を作ったとしても、結局は同じになるというものです。これを役割分担だと割り切ることができれば楽かもしれませんが、心身を擦り減らして働く者にとっては、自分だけがなぜこんなに大変で、あいつはどうして何もしないで涼しい顔をして過ごしているのかと感じてしまうのも無理からぬことかもしれません。
これ以外にもこの譬話をめぐって不当に感じてしまうことがいくつもあるとは思いますが、しかしこれらの理解はこの譬話を複雑に考えすぎており、いずれも的外れだと言えます。この物語は実際には単純な論理で貫かれているからです。この譬話を解釈するうえでのキーワードは3節と6節に用いられているἀργός(アルゴス)という語です。これは「労働/仕事」を意味する名詞のἔργον(エルゴン)に否定の接頭辞のἀ(ア)をつけて形容詞にしたものであり、「仕事がない」状態を表します(田川建三訳、佐藤研訳[岩波訳]参照)。しかし、代表的な日本語訳聖書(口語訳、新共同訳、新改訳2017、協会共同訳)はいずれも「何もしないで」と翻訳しており、確かにこれもἀργός(アルゴス)に含まれる意味には違いないのですが、これではブラブラして何もせずにサボっている人をイメージしてしまいます。ですから、この譬話の評判が悪いのは従来の日本語訳聖書に起因する部分も大きいと言えるのです。
さて、冒頭に示した私訳では、3節のἀργός(アルゴス)には「仕事にあぶれて」と少し踏み込んだ訳語を充てました。ですから、6節のἀργός(アルゴス)も「仕事にあぶれて」と訳語を合わせたいところではあるのですが、それでは意味不明になってしまうので、「仕事をしないで」と直訳しました。しかし、6節のぶどう園の主人の「どうしてここであなたたちは日がな一日仕事をしないで立っているんだい」という問いに対する、7節の労働者たちの「誰も自分たちを雇ってくれなかったからだよ」という応答からも、この人たちは「何もしないで」広場でブラブラ遊んでいたのではなく、「仕事にあぶれて」しまったために、半ば諦めつつも、何とか仕事にありつきたいと思って、早朝から夕方まで広場に立っているほかなかったことがわかるのです。
そして、この観点から譬話の全体を眺めると、この物語において広場に立っている人たちが一貫して「労働者(ἐργάτηςエルガテース)」(1、2、8節)と呼ばれでいることにもイエスの視座が垣間見えるのです。つまり、広場に日がな一日立っていた人たちはブラブラして遊んでいたのではなく、仕事をしたくても仕事がなかった人たちであり、この人たちも全て「労働者」だと言っているということです。ここには住む家がなくドヤ街などで暮らす人たちが働かずに怠けている「ホームレス」と決めつけられている社会の在り方を批判し、この人たちは種々の事情で仕事をしたくても仕事がなかったり、様々に工夫して日銭などを稼いだりしている「野宿労働者」ではないかとするある種の拘りに類する理解をイエスがすでに示していたことをうかがわせます。
このようにぶどう園の労働者の譬は仕事にあぶれた日雇い労働者の悲哀を背景として物語られているのです。この人たちは前の日もこの日も次の日も仕事にあぶれてしまう人たちだったのです。その理由は様々でしょうが、手配師に労働力としては使いものにならないからと端から相手にすらされず、最後まで誰にも雇って貰えなかったのです。それに対して、最初に雇われた人たちは一日の重労働に耐えられる体力があり、そのためにまっさきに雇ってもらえる人たちだったのです。昨日も今日も明日も誰かしらに雇ってもらえるからこそ、ぶどう園の主人に向かって、「この最後の奴らは1時間稼いだだけじゃないか。しかも、あんたは一日の重労働と猛暑を耐え抜いた自分たちをこいつらと同じ稼ぎにしやがった」と堂々とクレームを言えたのではないでしょうか。むろん、この人たちもまた日雇い労働という不安定な生活を余儀なくされていた人たちでもありますので、ぶどう園の主人の態度が不遜に思えたのも致し方のないことかもしれません。
しかし、日がな一日仕事にあぶれた人たちは誰にも雇ってもらえず、その姿は――ぶどう園の主人も最初はそう思ってしまっていたのかもしれませんが――働きもせずに広場にたむろする集団にしか見えなかったのかもしれません。しかし、実際にはこの人たちは雇ってくれる人がいないだけであって、決して遊んでいるわけでも、サボっているわけではないのです。1時間であっても働きたかったのですから。したがって、イエスがこの譬話を通して伝えているのは、仕事にあぶれて誰にも雇ってもらえない最も困っている人たちにこそ、まっさきに報酬が支払われるのが神の王国の論理だということです。それはこの世界の論理からすると確かに矛盾であり、不条理かもしれませんが、最も困っている人にフォーカスを当て、一点突破しようとする偏った物の見方と強引さからイエスらしさがひしひしと伝わってきます。
このような譬話の解釈を聞いて、何を甘いことを言っているのかと思うかもしれません。イエスの時代にもこのようなイエスの偏った物の見方は受け入れられなどしなかったのですから、それがこの世界の常識なのでしょう。しかし、「ぶどう園の主人」(神)にしか雇って貰えなかった「労働者たち」は、労使間の団体交渉もなく、労基署が守ってくれることもない社会の周縁に追いやられていた人たちなのです。これは1時間しか働かない上級国民の話ではなく、国会で1時間ほど居眠りして歳費(給与)を掠め取る政治家の話でもないのです。現代の野宿労働者や生活困窮者が置かれている――絶対的貧困や相対的貧困として広がっている――日本社会の現実の問題をも射抜くイエスの視座がどこに置かれていたのかを如実に示す物語なのです。イエスは来る日も来る日も仕事にあぶれて最も困窮している労働者の目線から社会を見ていたのです。その意味では、この譬話は「ぶどう園の労働者の譬」ではなく、「仕事にあぶれた労働者の譬」と呼ぶのが相応しいと言えます。
3月5日の灰の水曜日から始まったレント(受難節)というイエスの受難を覚えるとき、登場人物の誰の目線からこの譬話を読むのかが問われています。あなたはどう読みますか。(小林昭博/酪農学園大学教授・宗教主任、デザイン:宗利淳一)