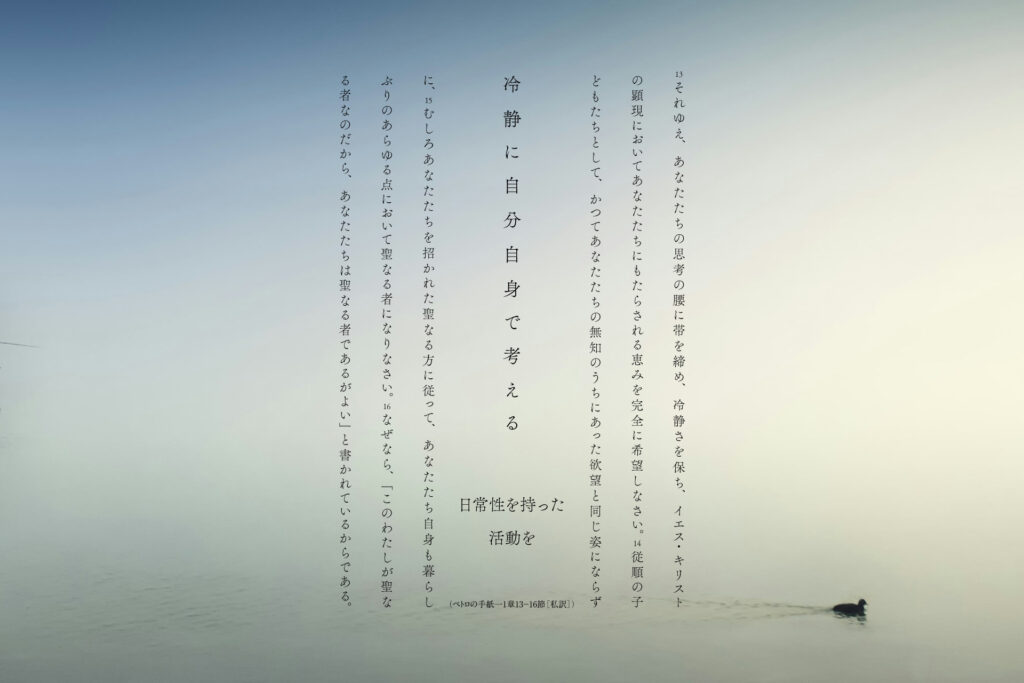冷静に自分自身で考える
――日常性を持った活動を――
13それゆえ、あなたたちの思考の腰に帯を締め、冷静さを保ち、イエス・キリストの顕現においてあなたたちにもたらされる恵みを完全に希望しなさい。14。従順の子どもたちとして、かつてあなたたちの無知のうちにあった欲望と同じ姿にならずに、15むしろあなたたちを招かれた聖なる方に従って、あなたたち自身も暮らしぶりのあらゆる点において聖なる者になりなさい。16なぜなら、「このわたしが聖なる者なのだから、あなたたちは聖なる者であるがよい」と書かれているからである。
(ペトロの手紙一1章13−16節[私訳])
Ⅰペトロ書1:13−16は、理知的に物事を考え、冷静にその本質を見極め、思慮のない欲望にまみれたこの世界に迎合することなく、神に召された者に相応しい生き方をするように勧めています。これはかなりハードルの高い要求です。その行き着く先は、清貧のような敬虔で遜った生き方になることもあれば、選民意識やエリート意識に凝り固まった傲慢な生き方になってしまうこともあるように感じられます。とはいえ、自分自身で物事をしっかりと考え、冷静さを保って生きるというのは、現代の国際社会および日本社会の混沌とした情勢を考えると、とても大切なことを伝えていることは間違いありません。
今回ギリシャ語原文を一読するまでは、これまで新共同訳聖書の訳文に慣れ親しんできたこともあって、このテクストは忠誠心に溢れた従順な人間になるよう勧めているとばかり思っていました。というのも、新共同訳はⅠペトロ書1:13−16を以下のように翻訳しているからです。
13だから、いつでも心を引き締め、身を慎んで、イエス・キリストが現れるときに与えられる恵みを、ひたすら待ち望みなさい。14無知であったころの欲望に引きずられることなく、従順な子となり、15召し出してくださった聖なる方に倣って、あなたがた自身も生活のすべての面で聖なる者となりなさい。16「あなたがたは聖なる者となれ。わたしは聖なる者だからである」と書いてあるからです。
(ペトロの手紙一1章13−16節[新共同訳])
とりわけ新共同訳の「心を引き締め」「身を慎んで」「従順な子となり」といった表現から、このテクストは従順な人間になるよう求めていると思い込んでしまっていたのです。もっとも、このような思い込みをしてしまったのには、ほかにも理由があります。それはⅠペトロ2:13−3:7が「市民の王に対する服従」(2:13−17)、「召使の主人に対する服従」(2:18−25)、「妻(女)の夫(男)に対する服従」(3:1−7)を命じており、君主制(政治統治機構)、奴隷制(身分制度)、家父長制(男性中心主義)を肯定するのみならず、それらがより強固になるように支えてきたからにほかなりません。
しかし、今回このテクストを一読して、Ⅰペトロ書1:13−16に関しては、これまで持っていた印象は一面的なものだということに気づかされました。この印象は新共同訳と私訳を比較することで分かっていただけると思いますが、ここでは以下の3つの表現に的を絞って説明をしてみたいと思います。
|
新共同訳 |
私訳 |
|
心を引き締め |
思考の腰に帯を締め |
|
身を慎んで |
冷静さを保ち |
|
従順な子となり |
従順の子どもたちとして |
最初の「心を引き締め」ですが、この翻訳では、決意をしたり、心持ちをしっかりしたりするといった内面の問題や精神論を想起してしまいますが、原文は「思考の腰に帯を締め」です。「腰に帯を締める」に「思考」を意味するδιάνοια(ディアノイア)をくっつけているのですが、ほかには出て来ない変わった組み合わせの表現です。もっとも、ディアノイアは「思考」「思念」「理解「考え方」「知性」などの意味ですから、「思考の腰に帯を締め」とは、心の持ちようが問題になっているわけではなく、自分自身で物事をしっかり考え、理解しようとする理知的な振る舞いが求められているということです。
次の「身を慎んで」ですが、この翻訳だと、公序良俗に反しない真っ当な生き方をする「慎み深さ」が求められているような印象を受けてしまいますが、原語のνήφω(ネーフォー)という動詞は「酒を飲んでいない」「酒に酔ってない」「しらふである」が本来の意味です。そして、それが比喩的に用いられて、「自制する」という意味でも使われます。おそらく、新共同訳はこのニュアンスで口語訳の「身を慎む」を継承しているだと思います。しかしながら、ここで問題になっているのは「しらふでいる」ことですので、この世の潮流に巻き込まれたり、流されたりせずに、「冷静でいる」ことや「醒めている」状態を保ち続けるよう勧めているのです。
最後の「従順な子となり」ですが、この翻訳だと、やはり従順な人間になることを要求されているように思えるのですが、原語は「従順の子どもたちとして」です。「〜の子どもたち」はヘブライ語的な表現であり、「〜に属する者たち」を意味します。ここでは1:2の「イエス・キリストの従順と血の注ぎへと〔召されている者たち〕」としてのⅠペトロ書の受信人である教会の人たちを指して用いられています。そして、この「従順の子どもたち」は後続の15、16節において「聖なる者」と言い換えられています。ですから、「従順の子どもたち」とは、「聖なる方」(神)に招かれた「聖なる者」として、「暮らしぶりのあらゆる点において聖なる者」になるよう勧められていますので、この世と迎合したり、妥協したりすることのない生き方が求められていると言えるのです。
このようにⅠペトロ書1:13−16は、自分自身で理知的に物事を考え、冷静に物事の本質を見極め、この世界と迎合することなく、神に召された者として生きることが勧められているのです。2026年1月のキリスト教の小部屋において「混沌(カオス)の世界に生きる一年を」という文章を書きましたが、その1ヶ月後の日本の政治の喧騒がここまで酷くなるとは想像していませんでした。その意味でも、担当者が今月の聖書としてⅠペトロ書1:13−16を選んだのはまさに慧眼と言えます。なぜなら、この喧騒状態に乗っかってしまうことは、同じ論理構造に絡め取られることであり、この喧騒と混沌の渦中にあるからこそ、冷静に醒めた視点でじっくりと考え、自分がすべきことに全力を傾けていくことが大切なのです。
この原稿を書いている最中に、わたしも委員として属する日本キリスト教団北海教区平和部門委員会から、原発、LGBTQ+、外キ連などの集会案内や活動案内が届きました。この喧騒にもかかわらず、しかも北海道も雪害で大変だったのですが、通常営業というか、粛々と活動をしている人たちの姿に接して、まさに「暮らしぶりのあらゆる点において」冷静に自分自身で考え、日常性を持って活動することの大切さを改めて実感させられています(まずは学生たちと卒論を完成させます)。
(小林昭博/酪農学園大学教授・宗教主任、デザイン/宗利淳一)
キリスト教の小部屋アーカイブはこちらから